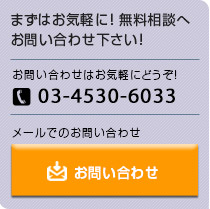- ホーム >
- 中小企業向けの退職金・企業年金制度とは
当社ではそれぞれの基本的な仕組みの違いをお客様にご理解いただき、退職金の社外積立制度、福利厚生制度としてどの企業年金が最適であるかの判断材料をご提供しています。
日本の年金制度は、公的年金制度と、公的年金を補完する私的年金制度の2つに大きく分かれます。公的年金制度には、国民年金制度と厚生年金制度があります。私的年金制度には、企業が設立しないと加入できない企業年金と、それ以外の個人年金に分類されます。
日本の年金制度は3階建てといわれますが、保険会社などが売り出す個人年金まで含めると、4階建ての構造になっています。


現在の企業年金制度は、厚生年金基金、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の3種類があります。企業が従業員の退職後の所得保障のために独自に運営をしています。
企業年金制度は従業員の定年退職時に一時金を支給する退職一時金制度を前身としています。退職一時金制度は、江戸時代の「のれん分け」 に由来すると言われており、明治期以降、熟練労働者の足止め策の一つとして普及・慣行化していきます。

しかし、戦後の高度経済成長に伴い退職者数が急速に増加すると、退職金の支払負担が増加し、企業経営を圧迫し始めます。このころから退職一時金の平準化が企業経営上の課題として注目されるようになります。
そのような状況を背景に、経済界からの要望により、1962年に当時の大蔵省の所轄のもと『適格退職年金制度』が創設されます。これが税法上の優遇を伴う初めての企業年金制度です。
その後、当時の厚生省の所轄のもと1996年に、国の厚生年金の一部を民間に代行させ、あわせて企業独自の給付を上乗せして支給する『厚生年金基金制度』が創設されました。
退職積立金の負担の平準化や税制上のメリットなどの点から、多くの企業で企業年金制度が導入され、退職一時金の一部または全部を企業年金制度へ移換していきます。
『適退職年金制度』と『厚生年金基金制度』が企業年金制度の主流となり、従業員の老後の所得保障に大きな役割を果たしましたが、バブル経済が崩壊すると、年金基金の運用実績が急速に悪化したことで、『厚生年金基金制度』の代行部分の積立不足が発生し、社会問題となりました。
また、『適格退職年金制度』はあくまでも税法上の規定で、財政の健全化を検証する仕組みが不十分なものでした。そのため、景気や運用の低迷によって積立不足が慢性化しやすく、その結果受給権の保護が危ぶまれる状況となり、法的整備が急務となりました。
企業年制度の積立不足や受給権保護の問題を解決するため、国は2001年に『確定拠出年金法』を、2002年に『確定給付企業年金法』を制定しました。これにより企業年金制度が再編され、選択肢は大幅に拡大されましたが、その一方で『適格退職年金制度』は廃止となりました。
企業年金制度の改革は現在も進み、各企業はそれぞれのニーズと時代に合わせて制度をどのように再構築していくかが課題となっています。

ギモンを解決! 適格退職年金制度とはどのような制度だったの?


適格退職年金制度とは、企業が信託会社や生命保険会社等、外部金融機関と契約し、従業員に年金給付を行う制度です。一定の要件を満たす契約について国税庁長官の承認を受けると税制上優遇が認められていました。
この適格退職年金制度は、設計の自由度が高く、中小企業にとっては運営のしやすい制度として重宝されていましたが、国税庁の管轄の制度のため脱税の有無のほうに重きがおかれ、受給権を確保させるための監督・指導体制は脆弱でした。
1990年代後半に低金利環境が続き、積立不足が拡大すると、こうした問題点が憂慮され、制度の見直しが議論されるようになりました。
適格退職年金制度の受給権確保や、積立不足の拡大といった点が問題になっていたからです。
ほぼ同時期に、当時の厚生省が企業年金制度について財政検証等の厳しい基準を設けますが、『確定給付企業年金法』と『確定拠出年金法』を受け皿として創設したことをきっかけに、問題を抱えた適格退職年金制度を一気に整理していくことが決まりました。
2002年4月1日以降は、適格退職年金制度の新規契約は認められなくなり、すでに適格退職年金制度を導入している企業は、他制度への移行が求められることとなったため、2012年3月31日をもって制度は実質的に廃止となりました。
ギモンを解決! 厚生年金基金とはどのような制度なの?


厚生年金基金制度は、企業や企業団体などが厚生労働大臣の認可を受けて特別法人(=基金)を設立し、その基金が従業員に年金給付を行う制度です。
本来は国が担うはずの公的年金(厚生年金)の運用・給付の一部を、企業が代行する仕組みとなっています。
企業は基金を設立すると、厚生年金の保険料の一部(代行部分といいます)を納付することが免除されるので、その分を自社の積立分と合わせて運用できます。

運用資金の規模が大きくなるため、好景気で運用状況が好調だった当時はスケールメリットを得ることができました。
ところが、バブル経済崩壊以降の景気悪化や運用利回りが低迷すると、多くの厚生年金基金が年金原資の積立不足に陥り、その負担に耐えられずに企業経営が傾く恐れまで出てきました。
これを受けて国は、企業年金制度の改革に踏み切ります。2002年に、企業の負担を軽減させるため代行部分を国に返して『確定給付企業年金』に移行することを可能としました。
同年には、企業会計基準が見直され年金の積立不足を決算書に反映させなければならなくなったことも追い風となり、改革以降、代行部分を返上し『確定給付企業年金』に移行する例が相次ぎました。
しかし、この改革で代行部分を返上できたのは、主に大企業が運営する厚生年金基金でした。国に返上するには代行部分の積立不足も埋め合わせしなければならず、中小企業が運営する厚生年金基金の多くは、積立不足の代行部分を抱えたまま返上ができない状態でした。
きっかけは、2012年のAIJ投資顧問による年金資産消失問題でした。
AIJ投資顧問が企業年金から受託し運用していた年金資産の大半を消失させていたことが明らかとなり、100以上の企業年金が被害を受けました。
これを契機に、厚生年金基金の代行割れ(基金の保有する資産が、公的年金の代行部分に必要な積立額に満たない状態)が社会問題となりました。
AIJ投資顧問会社の年金消失問題が厚生年金基金のあり方に大きな問題を投げかけたことで、国は厚生年金基金廃止の方針に大きく舵を切ります。
2014年に厚生年金基金制度を抜本的に見直す法律を施行しました。
これにより、厚生年金基金の新設が認められなくなったほか、財政が健全な基金を除いて解散または他の企業年金制度への移換が求められました。
再編後の企業年金制度は、確定給付型と確定拠出型にわかれており、それぞれ特徴があります。 退職金・企業年金制度の導入検討にあたっては、現行制度の実態、問題点などを把握し、見直しに至った理由や期待する効果を整理したうえで、それぞれの制度の長所・短所を比較して自社に相応しい制度を選定する必要があります。
確定給付型と確定拠出型の比較
| 確定給付型年金 | 確定拠出型 | |
|---|---|---|
| おもな制度名 | 厚生年金基金、確定給付企業年金 | 確定給付企業年金 |
| 仕組み | 給付額を保障。 | 掛金額を保障。 (*給付額は運用成果によって決まる。) |
| 掛金 | 数理計算によって算定。 (*運用実績などにより生じる過不足で掛金が変動する。) |
数理計算は不要。 運用実績にかかわらず、掛金は一定。 |
| 資産運用等 | 制度実施者(企業・基金)がまとめて運用管理を行う。 | 加入者である従業員が運用管理を行う。 (*資産は個人別に管理される。) |
| 給付 | 企業等が給付の算定方法を約束する。 | 年金額は個人の運用実績によって変動する。 |
| 企業会計上の取り扱い | 退職給付債務に基づいて負債および費用が計上される。掛金は費用として処理されない。 | 退職給付債務は発生しない。掛金は費用として処理される。 |
企業にとってのメリット・デメリット
| 確定給付型年金 | 確定拠出型 | |
|---|---|---|
| メリット |
給付額が約束された企業年金制度を有していることで採用面での競争力強化、従業員のロイヤリティ向上につながる。 効率的な資産運用によっては掛金の軽減が可能。 掛金拠出に税制優遇措置が講じられているため、退職一時金より効率的に資金準備ができる。 |
積立不足が生じないため、掛金の追加拠出が不要。 退職給付会計の対象外となるため、退職給付債務が生じない。 他社の企業型確定拠出年金から資産の受け入れが可能となるため、有力な人材の確保につながる。 |
| デメリット |
退職給付会計の対象となるため積立不足を会社の債務として認識しなくてはならない。 資産運用の責任を負う。 積立不足が生じる可能性があるため、追加拠出の可能性がある。 |
継続的な投資教育の実施義務がある。 勤続3年以上の自己都合退職者や懲戒解雇者について減額支給できなくなる。 |
従業員にとってのメリット・デメリット
| 確定給付型 | 確定拠出型 | |
|---|---|---|
| メリット |
給付の算定方法が確定しており、年金の受取り見込額がわかりやすいため、老後の生活設計が立てやすい。 資産運用は会社や基金が行うため、資産管理に気を使わずにすむ。 |
今いくら残高があるかすぐに確認できる。 運用方法や資産構成割合を自分で選択でき、運用が好調なほど高い給付が期待できる。 受給権が確立しており、勤続3年以上であればどのような理由でも減額されない。 自身のDC資産のみ管理/運用すればよく、現役世代やOBの資産の運用リスクを負うことはない。 |
| デメリット |
加入者ごとの年金資産が不明確。 勤続年数にかかわらず給付減額の可能性がある。(受給者も同様) 積立不足が発生し償却負担が重い場合、業績が圧迫されて給料などに悪影響を及ぼすことがある。 |
資産運用を自ら行わなければならない。 運用成績により給付が変動するため運用が不調であれば受給額が減る。 原則として60歳まで受給できないため、中途退職時の生活費や独立資金としては用いることができない。 |
退職金・企業年金の運営は、費用コストがかかるほか事務的な負担も多く、中小企業が単独で退職金・年金制度を持つことが難しい場合があります。
そこで、国や各種団体が援助する中小企業向けの退職金制度を利用する選択肢があります。これらの制度は、企業年金制度ではないですが、中小企業が退職金年金制度構築や見直しを行う際、退職金制度の社外積立先として利用検討がなされますので、代表的な中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度についても触れておきます。
中小企業向けに設けられた社外積立の退職金制度として、国が援助する中小企業退職金共済制度(中退共)があります。
中退共と類似した制度に、特定退職金共済制度(特退共)があります。こちらは国の援助はなく、商工会議所・商工連合会などが設立主体となっています。
| 中小企業退職金共済制度 (中退共) | 特定退職金共済制度 (特退共) | ||
|---|---|---|---|
| 運営 | 中小企業退職金共済事業本部 | (市町村や商工会議所) | |
| 加入者の条件 | 原則、社員全員加入 | ||
| 掛金額 | 2,000~30,000円の19段階 2,000~4,000は短時間労働者のみ |
1口1,000円で30口まで | |
| 退職金 | 基本退職金+付加退職金 掛金月額と納付月数で計算。 運用利回りによって付加退職金の上積みあり |
口数および加入期間で計算 | |
| 支給方法 | 原則一時金(一定条件の場合、分割も可) | ||
| 税制上の取扱い | 掛金 | 全額損金または必要経費 | |
| 給付 |
一時金払:退職所得 分割払い:雑所得(公的年金等控除の対象) |
||
| 給付の時期 | 退職時 | 退職時 | |
企業とは関係なく、個人で加入することができる制度には、個人型確定拠出年金(iDeCo)、国民年金基金、個人年金などがあります。(なお、国民年金基金は自営業者などの第1号被保険者が加入できる制度なのでここでは説明を割愛いたします。)
個人型確定拠出年金(iDeCo)
確定拠出年金は、会社が企業年金制度として採用する企業型確定拠出年金と、個人が自助努力の資産形成として任意で加入する個人型確定拠出年金の2つがあります。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は、法改正により、2017年1月から加入対象範囲が拡大されました。
法改正によって、これまでの加入対象者に加え企業年金加入者・公務員共済等加入者・私学共済加入者・国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)の方も、原則、個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することができるようになりました。
個人型確定拠出年金(iDeCo)は個人で加入して利用する制度ですから、加入者個人(従業員)が運営管理機関(金融機関等)を選定し、掛金の拠出や制度事務手数料を従業員が支払います。
掛金の支払い方法は、「個人口座からの引き落とし」または「給与天引き」のいずれかが選択できます。
従業員が「給与天引き」を選択した場合、会社は従業員から預かった掛金を「国民年金基金連合会」へ振込みます。
基本的には従業員の責任において加入も運用も行われますが、「従業員の自助努力支援」の観点から、社内の利用希望者を集めて制度説明会やライフサポートセミナーを行う企業もあります。
当社でもライフサポートを含め従業員向けセミナーの企画や開催支援を承っております。
個人年金
個人年金には、銀行、保険会社、証券会社、農協などの金融機関から販売されている様々な年金商品があり、これらは個人の意思で加入をします。
ただし、財形年金制度は個人型に分類していますが、制度を導入している企業の従業員のみが対象となります。
通常は、お勤め先の企業が取り扱い金融機関を選定し、労使協定を結んだ上で導入しますので、企業によって取り扱う運用商品も異なってきます。
企業が福利厚生制度として採用しなければ、従業員は加入することはできません。